※このサイトは商品プロモーションを含みます。
こんにちは「さぁさ」です。
1月の半分が過ぎ、そうこうしている内にあっという間に2月です。
2月と言えば「節分」です。
節分とは日本古来からある伝統行事で「豆まき」をするこということは
皆さんもご存じとは思いますが
なぜ節分では「豆まき」をするのでしょうか?
2025年の「節分の日」は2月2日

「節分」とは、季節の変わり目に邪気や悪いものを払い、新しい年に福を招く日本の伝統行事です。
豆まきは室町時代から始まったといわれており、当時は豆でなくお米をまいたとされております。
「節分の日」は「立春の前日」とされておりその年によって「節分の日」は異なります。
豆まき
節分で有名なのは「豆まき」です。昔は病気や災害などは鬼の仕業だと考えられていました。
鬼を退治して厄災を取り除くという目的で豆まきが行われています。
豆まきには「鬼は外」と外に向かって豆をまき、鬼が戻ってこないようにすぐに窓を閉めます。
その後「福は内」と室内に向かって豆をまきます。
まき終わったら、自分の年齢の数、あるいは1つ加えた数の豆を食べ
その年の無病息災を祈ります。
※お子さんが豆を食べる時は喉に詰まらせないように注意してあげてください。
子供と楽しみながら行おう
お子さんと楽しみながら豆まきが出来るグッズも簡単に購入できます。
またペットへの被り物としてのグッズもあります。
柊鰯(ひいらぎいわし)、焼い嗅がし(やいかがし)
節分には鰯の頭を柊の枝に刺して玄関先に付ける「柊鰯」または「焼い嗅がし」
という風習もあります。
鬼は鰯の匂いが苦手で柊のトゲで鬼を刺すと考えられていました。
恵方巻き
恵方とは年神様がいるとされる縁起の良い方角のことで年によって方角が変わります。
恵方を向いて「太巻き」を食べる風習を「恵方巻き」と言います。
太巻きは七福神にちなんで7種の具を入れることが定番で
福を逃がさないように太巻きは切らずに食べることが推奨されています。
頭の中で願い事を唱えながら黙って食べると願いが叶うといわれています。
2025年の恵方は「西南西」の方角です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
節分とは日本古来からの伝統的な行事です。
お子さんやペットと一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか。
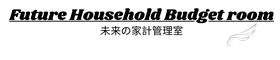


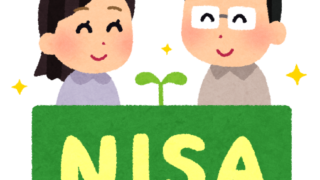









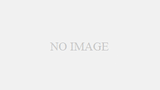
コメント